生活の実感と、政治のリアルをつなぐパパ視点の見解
【選挙明けの朝、変わらない日常】
選挙が終わっても、朝起きたら電車は止まってないし、子どもの準備も変わらない。
でも、選挙で見えてきたのは、「政治って本当に僕たちの生活とつながっている」という現実でした。
【① 自公与党、参議院も過半数割れ】
改選125議席のうち、自民は39、公明は8。つまり47議席にとどまり、必要な50議席に届かず。これで上院も与党が過半数を失うのは初めてです。
1985年以来、参議院と衆議院の両方で与党が少数勢力になるのは初。
石破首相は続投の意向を明言しているものの、内部からは批判も出ています。
【② なぜ、それが生活と結びつくのか?】
物価高への対応、社会保障、育児支援、税制改革—–
すべての政策は、国会で決まります。
有権者の多くが「選挙に行っても意味ない」と感じていた結果が、
“給料が増えないのに税金だけ増えている”という現実に重なって見えるのです。
【③ 投票率と無党派の存在感】
20代・30代の投票率は依然として低く、無党派層の票動向が次第に影響力を持ち始めている。
一方で、新興勢力(維新、国民民主、参政党など)が躍進し、選択肢が広がったのも事実。
【④ 結果が示したのは、“変われるかどうか”の試金石】
与党の大敗には、生活者の“怒り”や“不安”がにじんでいる。
特に物価、円安、エネルギー価格の上昇に対する政府対応への不信感は根深い。
【⑤ でも、見えた“希望”もある】
・SNSで若い世代が政治について語る場面が増えた
・小さな政党が独自の言葉で支持を集め始めた
・「何も変わらない」から「少しずつでも動かす」空気が出てきた
【⑥ パパ視点で伝えたいこと】
子どもが大人になったとき、
「なぜ僕たちの世代は選挙に行かなかったの?」と聞かれたくない。
“選ばなかった”くせに、財布を嘆くのではなく、
「一票を投じた人たちが、たとえ少しでも変えようとしていた」
その姿を、ちゃんと未来に残しておきたい。
【まとめ】
- 自公は参議院でも過半数を失い、議会は不安定に
- 選挙は政治だけじゃなく、私たちの暮らしに直結している
- 投票率、無党派勢、若者の興味変化が未来を左右する
- 「政治は変わらない」ではなく、「なぜ変わらないのか」を問うことが第一歩
▶︎次回予告
「インテルが15%の大規模リストラを発表。
AI時代、“仕事を奪われる”のではなく、“求められるスキルと形が変わるだけ”という見方」
急激な変化の背後で、働くあなたが今知っておくべきこと。
次回は、「AIと働き方のリアル」について現場目線で掘り下げます。

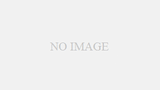
コメント