■ 「子どもが生まれない国」になったという事実
2024年、日本の出生数がついに70万人を下回った。
一つの節目、そして“予測はしていたけど、現実になった”という日だった。
1970年代には200万人を超えていたこの国の出生数は、今やその3分の1以下。
ニュースを見た瞬間、「これは未来の話じゃない。今、自分が生きている社会の話だ」と思った。
■ 僕も、“もう一人ほしい”けど現実は厳しい
実はうちにも子どもがいる。
そして正直に言うと、「もう一人ほしい」と思ったことは何度もある。
でも――
- 教育費への不安
- 共働きでギリギリの毎日
- 家計と時間とメンタルの限界
この国では、“産めるけど産まない”んじゃなくて、
“産みたいけど、怖い”人が増えている。
■ 少子化の影響は、じわじわ“生活”に降りてくる
出生数の減少は、将来の話でもあり、今の話でもある。
✅ これから現実になる変化:
- 保育園・学校の統廃合 → 通園・通学の距離が伸びる
- 郊外や地方のサービス縮小 → “不便”が日常になる
- 働き手不足 → 待ち時間、サービスの質に影響
- 社会保障のバランス崩壊 → 働く世代の負担増加
つまり、「子どもが減る」というのは、「社会が縮んでいく」ことそのもの。
■ じゃあ、僕たちにできることは?
少子化は政治や制度の問題。でも、それだけじゃない。
僕たちにもできることは、たくさんあると思っている。
✅ たとえば:
- 子育て中の人を孤立させない。声をかける、話を聞く
- 働く親への配慮を“特別扱い”じゃなく、“当たり前”にする
- 他人の子も「社会の子」として関わる
- 自分自身の家族観・生き方を見つめ直す
社会は、制度だけじゃなく「空気」で変わる。
それを作るのは、僕たち一人ひとりだ。
■ おわりに
「出生数が70万人を切った」って、正直なところ、漠然と怖い。
でもそれ以上に思ったのは、“自分の選択”と向き合うタイミングが来ているんだということ。
産む、育てる、支える、見守る――どの立場であっても、
「子どもが減っていく国で、どう生きるか」は、もう誰もが当事者のテーマ。
小さな行動が、誰かの“育てる選択”の後押しになるかもしれない。
この現実を、静かに受け止めながら、僕は今日も家族と暮らしている。
▶︎次回予告
次回は、「通勤時間ゼロが最強?リモートワークが“生き方”を変える理由」をお届けします。
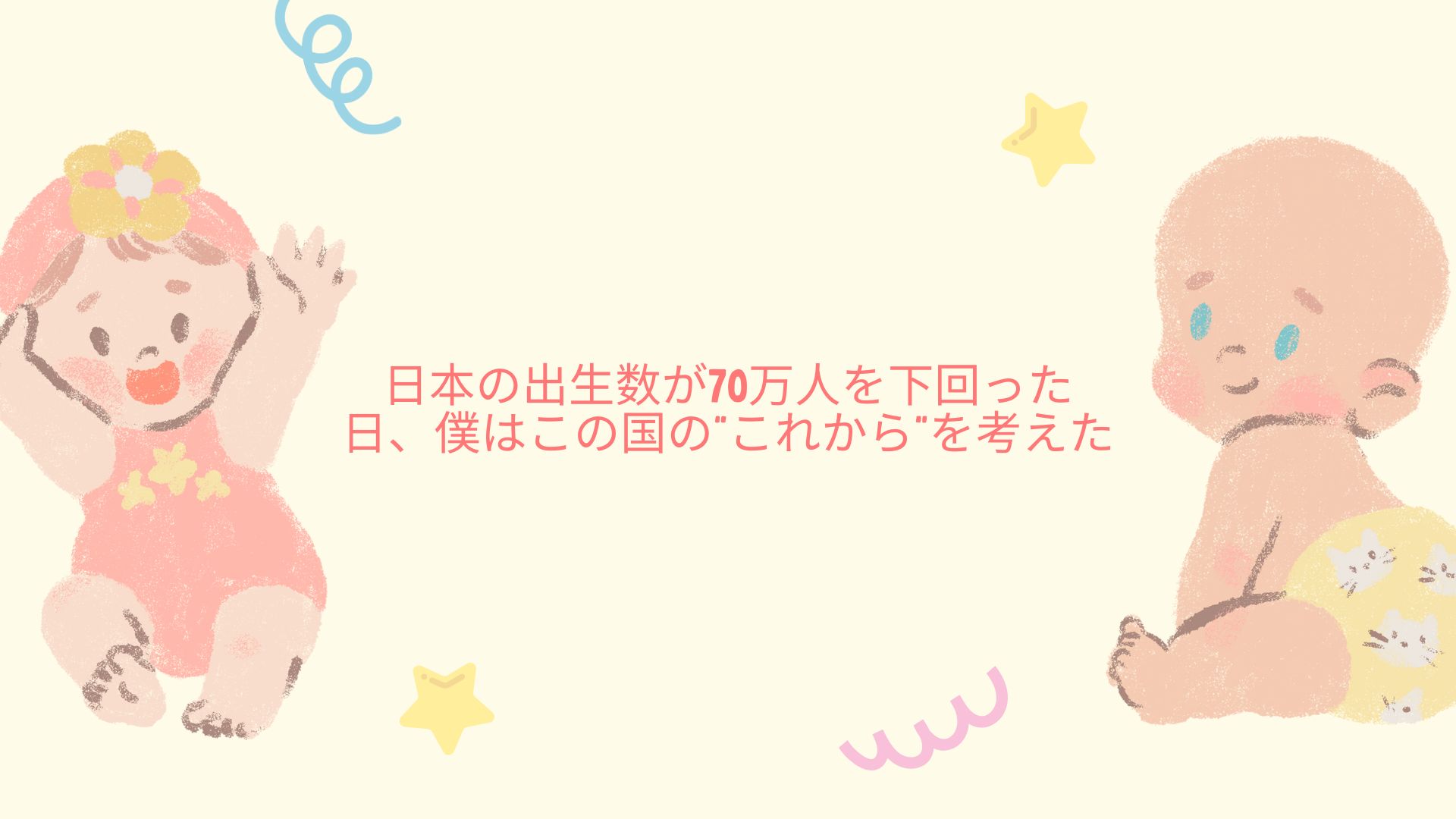
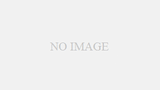

コメント