■ 感染が増えている。でも、それって“自己責任”なの?
先日アベマニュースで、性感染症の感染拡大が取り上げられていた。
特に梅毒の感染者数が2024年に過去最多を更新。若年層の間で急増しているという。
SNSを見れば「遊んでるからだろ」「自業自得」という声があふれていた。
でも僕は、**それを“個人の問題”だけで片づけてしまっていいのか?**と思った。
■ 性は自由になった。でも、教育は止まったままだ
マッチングアプリ、SNS、自由な恋愛。
性の在り方は、間違いなく多様になった。
でもそれに見合うだけの「性教育」や「知識のアップデート」は追いついていない。
僕らの頃と同じく、「コンドーム使いましょう」「病気に気をつけましょう」で終わっている。
- なぜ感染するのか
- どう予防するのか
- 症状が出ないときにどうすればいいのか
そんな“実際の行動に落とし込める知識”は、学校でも家庭でも話されない。
結果、YouTubeやSNSが頼りになり、誤った情報で動く人も出てくる。
■ 自己責任論は、現実を置き去りにする
性感染症は、症状が出ないケースも多い。
気づかないまま感染を広げてしまう人も多い。
それを「本人が悪い」で済ませるなら、社会ができることはどこにもない。
- 若者が気軽に検査できる場所や仕組みがあるか?
- 検査キットは高くないか?アクセスしやすいか?
- 恥ずかしいという気持ちを乗り越える情報環境があるか?
病気そのものより、無関心と偏見が感染を広げている。
責任の矢印を“感染者個人”に向けるより、社会が“構造的にどこで止められるか”を考えることが必要だ。
■ 僕らにできることは、“語れる空気”をつくること
性感染症は、ちゃんと予防できるし、ちゃんと治療もできる。
でも一番難しいのは「話せないこと」だと思う。
だからこそ大事なのは:
- 偏見でジャッジしない
- 情報を得る努力をやめない
- 話題にしても恥ずかしくない雰囲気をつくる
性や感染症を「恥」とせず、「正直に話せること」を評価できる空気を、
まずは僕ら世代からつくっていけたらと思う。
■ おわりに
性感染症の拡大は、「その人の選択が悪かった」じゃなくて、
「社会の準備が足りなかった」という側面が確実にある。
性の自由を叫ぶなら、その先にある教育とサポートも、ちゃんと整えていくべきだ。
無関心も、黙認も、偏見も、感染症を助長する一因になる。
今、自分がどこに立っているのか。誰を守れるのか。
考えるきっかけにしてもらえたら、うれしいです。
▶︎次回予告
次回は、「家でも会社でも話が伝わらない…。僕がやってる“伝え方”の工夫5選」をお届けします。
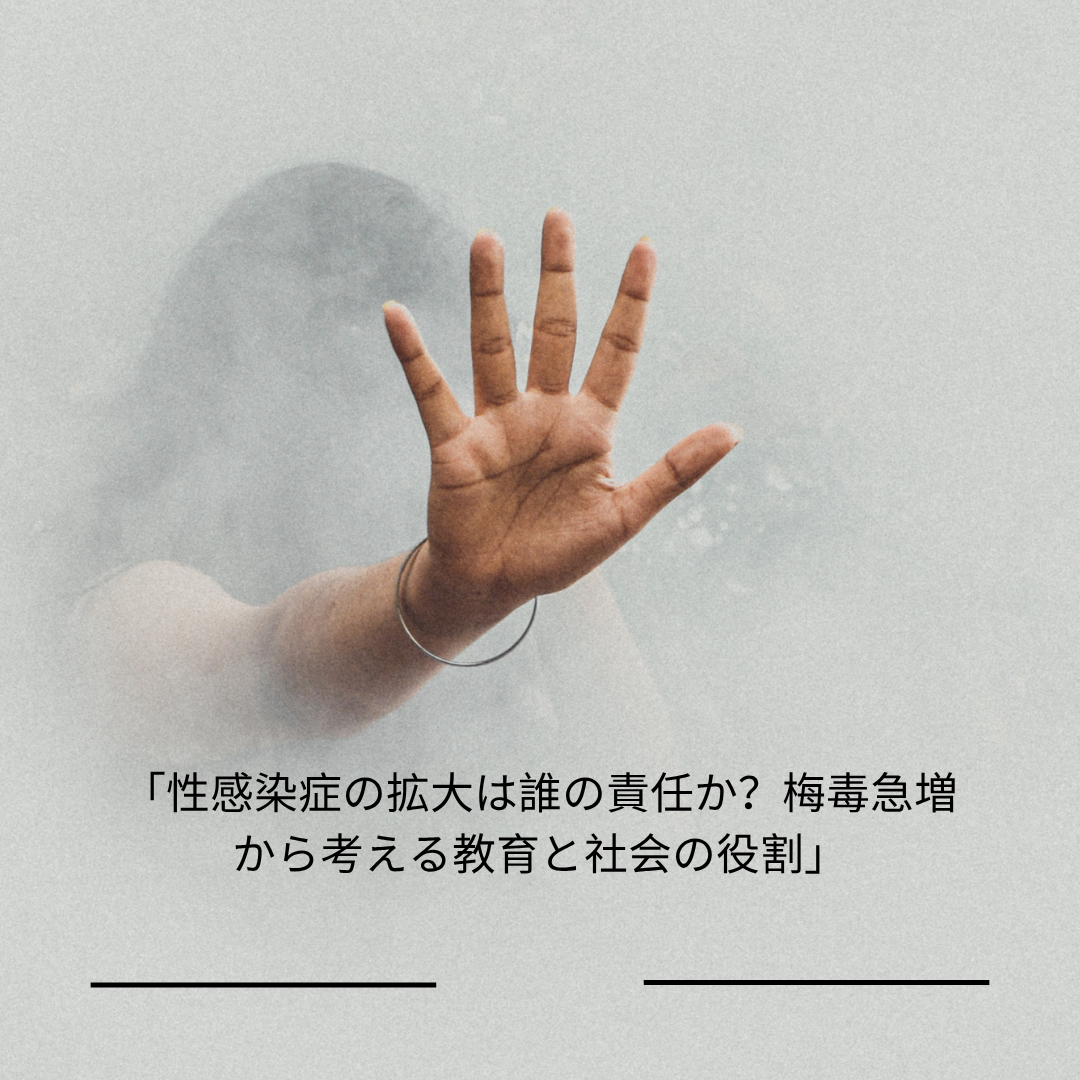


コメント