「選挙?どうせ何も変わらないじゃん」
若いころの僕も、そう思ってた。
でも今、2児の父になって、生活のこと、将来のことを考えるようになって気づいた。
政治は、めちゃくちゃ“日常”に食い込んでる。
物価、教育、育児、働き方、老後――。
気づいたら、全部“誰か”に決められてる。
その「誰か」を選べるのが、選挙だ。
【1. 政治は「選挙に行かない人」の暮らしも決めている】
たとえば最近、保育料が無償化された。
医療費が一定年齢までは無料。
高校の授業料がタダになる家庭もある。
…これ、政治が決めてる。
そしてその政治家を選んだのは、「投票した人」だ。
つまり、「選ばなかった人」も、勝手にその決定の中で生きることになる。
だから、「関係ない」は、もう通じない。
【2. 組織票に“勝てる”時代が始まっている】
よく言われる。「どうせ組織票が勝つでしょ」って。
でも、それを覆す出来事が、都議選でも起きている。
– SNSで個人候補がバズり、無所属で当選
– 市民ボランティアの草の根運動が、自民党候補を破った
– 地域課題を発信し続けた若手候補が、労組系を抜いた
もう、“組織”じゃなく“共感”が勝つ時代に入ってきている。
情報発信力、つながり、想い――それが人を動かしている。
【3. だからこそ、「僕たち」が投票すべき理由】
– 子育て世代の声を通したい
– 教育費を下げてほしい
– 自分たちの働き方を良くしてほしい
そのためには、“若い世代の投票率”がカギになる。
選挙に行かない限り、政治家は「その層向け」の政策をやらない。
逆にいえば、投票率が上がれば、政策は動く。
【4. 投票先がない?比べれば全然違う】
– 働き方改革をどれくらい本気でやってる?
– 教育無償化は実現する?財源は?
– 外国人労働者の受け入れ方針は?
– 増税と社会保障のバランス感覚は?
ちゃんと見れば、各政党、候補者ごとに「価値観」がにじんでいる。
完璧な人なんていない。
でも、自分の暮らしに近い感覚を持っている人に託すだけで、違う未来になる。
【5. 迷ったら、“この人と飲みに行きたいか?”で選べばいい】
本当に迷ったら、堅苦しく考えなくていい。
僕はこう考える。
「この人と飲みに行って、話が合う気がするか?」
価値観が近い人。子育てしてる人。会社員として悩んできた人。
そんな候補者を選べばいい。
選挙は正解探しじゃない。「選ぶこと自体」が、もう意味なんだ。
【おわりに:僕らはもう、“選ばれる側”ではない】
大人になるって、社会に参加することなんだと思う。
いつまでも「誰かが決める」「誰かがなんとかしてくれる」じゃなく、
自分で「誰に任せるか」を選ぶ。
選挙はその手段。
投票所に行くのは、自分の生活を守る行動だ。
たった10分の行動が、
これからの10年を少し変えるかもしれない。
▶︎次回予告(更新版)
「イオンでXRP導入。仮想通貨の時代は“もう始まっている”?」
ついに日本の大型小売店が暗号資産を決済に活用する時代に突入。
“現実の経済”に組み込まれ始めた仮想通貨と、その本質的な意味について掘り下げます。

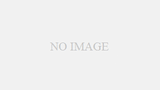

コメント