〜エリア選び・優先順位整理・理想と現実のギャップ調整〜
はじめに|15年目の家に、違和感が積もっていた
「まだ築15年だし、壊すには早いよな」
そんな空気が、どこか家族の中にあった。だけど、両親の本音は違っていた。
- 子どもが独立して、持て余す2階の部屋
- 無理な間取りで動線が悪く、暮らしにくい
- 階段の上り下りが少しずつ負担に感じてきた
- それでも、住宅ローンはまだまだ残っている
そんなとき、地域の地価がここ数年で大きく上がっていることが分かった。
不動産会社に査定を依頼したところ、土地の評価額が想定以上で、ローン残債を圧縮できる見込みがあると判明。
「だったら、“今”動いた方がいいかもしれない」
感情だけでなく、数字と生活の両面から合理的に判断して、
実家を建て替えるという決断を家族で下した。
そこから始まったこのプロジェクトで、僕が強く感じたのは——
「家を建てる前にやるべき準備こそ、住み心地を決める」ということだった。
Step1|【エリアの再確認】土地はある。でも、それで本当にいいのか?
実家に土地がある=建てる場所は決まってる。
そんなふうに思っていたけど、今回はそこから見直した。
- 今後の暮らしに必要な病院、スーパーは近くにある?
- 平日と休日、昼と夜の雰囲気はどうか?
- 近隣の住民層や防犯面に変化はないか?
- 土地の資産価値は、将来も維持されそうか?
両親と一緒に、地図アプリで周辺を調べ、実際に歩いてまわり、役所で地域情報もチェックした。
その結果、**「やっぱり今の土地がいい」**と再確認できた。
決断の後押しになったのは、
「住み続けるにも、売るにも強い土地だ」と確信できたことだった。
Step2|【優先順位の整理】親の希望と、子ども世代の現実的な視点
建て替えを前にして、両親にはいくつか明確な希望があった。
- 来客用の和室と広い玄関
- 収納をたっぷりと
- 仏壇を置くための静かなスペース
- 1階で生活が完結する設計
一方、僕ら子世代が心配したのは、
- 「今後10年で、どれだけ来客があるのか?」
- 「掃除・冷暖房コスト・動線、全部負担にならない?」
- 「玄関の広さよりも、段差の少なさや回遊性では?」
話し合いを重ねて、お互いの希望と課題を整理した結果、
“必要な部屋”は「使う目的」と「頻度」が明確なものだけに絞ることに。
さらに、
「老後に向けて、掃除も移動もラクな“暮らしやすさ重視”の設計にする」
という共通方針をつくることで、プランが一気に進みやすくなった。
Step3|【理想と現実のギャップ調整】モデルハウスの魔力に飲まれない
展示場に行くと、テンションはどうしても上がる。
吹き抜け、オープンキッチン、造作家具、回遊式の動線、ハイドア——
その全部が欲しくなる。
でも、現実は違う。
あれは“フルオプションの夢の空間”であって、
標準仕様では絶対に手が届かないことを僕は知っていた。
そこでやったこと:
- SNSのマイホームアカウントを熟読
- メーカーの標準仕様とオプション表をすべて可視化
- 家具や家電を含めた総予算から「足し算」でなく「引き算」設計
結果、
「必要な場所にはしっかりお金をかけて、こだわりすぎる場所は削る」
という、現実的で後悔の少ない家づくりにつながった。
おわりに|家を建てる前に“話し合った時間”こそが価値だった
実家の建て替えは、ただ新しい家に住むという話ではなかった。
両親にとっては「老後の生き方の再設計」。
僕ら子世代にとっては「今後のサポートのしやすさ」を考えるきっかけだった。
話し合いは時に面倒で、意見も食い違った。
でも、そのプロセスを通じて、
- 何を優先して生きるか
- どこで暮らすか
- どんな家が家族にとって“ちょうどいい”のか
が、言葉になり、形になった。
家は見た目じゃない。
**「暮らしを整えるツール」**であり、
その土台を一緒につくれたことが、何よりの収穫だった。
▶︎次回予告
次回は、「内見や現地確認で見るべき10のチェックポイント」を紹介します。
図面では分からない“現地の落とし穴”や、実際に見ておいてよかった場所とは?
スマホで使えるチェックリスト付きでお届け予定です!


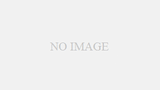
コメント