■ その日、ネットがざわついた
ある日、SNSで「フジテレビ」「やらせ」「ダルトン」がトレンド入り。
話題の発端は、フジテレビの人気番組に登場したダルトン氏による告発だった。
「これはリアルじゃない」「台本があった」
視聴者の共感を集めたシーンが“演出”で作られていた可能性が浮上し、ネット上では「裏切られた」と炎上。
一方でフジテレビ側は「事実に反する内容はない」と反論。
だが、この騒動は単なる「やらせ問題」ではない。
もっと根深い、“信じる”という行為そのものを問うものだった。
■ 視聴者が感じた「共感の裏切り」
視聴者は、「これはリアルだ」と信じた。
苦しみや乗り越えた背景、涙の意味に感動し、心を寄せた。
だからこそ、
「そんな感情まで演出だったのか」
と知ったときの衝撃は大きかった。
怒りというより、“感情を利用された”という悲しさ。
信じたからこそ、裏切られたと感じた。
■ メディアの“演出”はどこまで許されるのか
テレビに演出があるのは前提だ。
構成、テロップ、編集、時には再現ドラマ――どれも当たり前。
でも、今の時代は違う。
視聴者も当事者も、「声を発信できる」時代だ。
- SNSで本人が真実を語れる
- 嘘や違和感は一瞬で拡散される
- 「感情」で動く人がメディアを評価する時代
そうした土壌では、旧来の「ちょっと盛った演出」はもはや通用しない。
**「誰が、誰の物語を作っているか」**が常に問われている。
■ 誰が正しいのか?ではなく、「誰が消されたのか」
この騒動、単純な善悪の問題ではない。
- フジテレビ:演出はしたが、虚偽ではないと主張
- ダルトン:自分の本音や意思が歪められたと感じている
- 視聴者:「共感したのに、それが嘘だったのか」と怒っている
正義は1つじゃない。
でも、確実に言えるのは――
「誰かの物語」が、他者の都合で変えられてしまったということ。
■ パパとして思う:「情報との付き合い方」を教えられるか
自分の子どもがテレビやSNSで何かを見て「かわいそうだね」と言ったとき、
「でも、裏にどんな視点があるか考えてみよう」と伝えられるか。
見抜く力=生きる力になっているこの時代。
情報の波の中で、「自分の軸」を持てるようにするのが、大人の役目だと思う。
■ おわりに:演出より怖いのは“見たいものしか見ない”こと
人は感動したい、誰かを応援したい。
それは素晴らしい感情だけど、
その純粋さを利用されると、深く傷つく。
「これは誰の物語か?」
「その“演出”は誰のためか?」
そんな問いを持ちながら、これからも情報と向き合っていきたい。
▶︎次回予告(更新版)
次回は、「なぜキーエンスには“できない営業マン”がいないのか?組織の仕組みと文化を考える」をお届けします。
営業成績が圧倒的な会社は、どんな環境で人を育てているのか?
個人の能力ではなく、組織で“勝てる設計”を持つキーエンスの秘密を深掘りします。


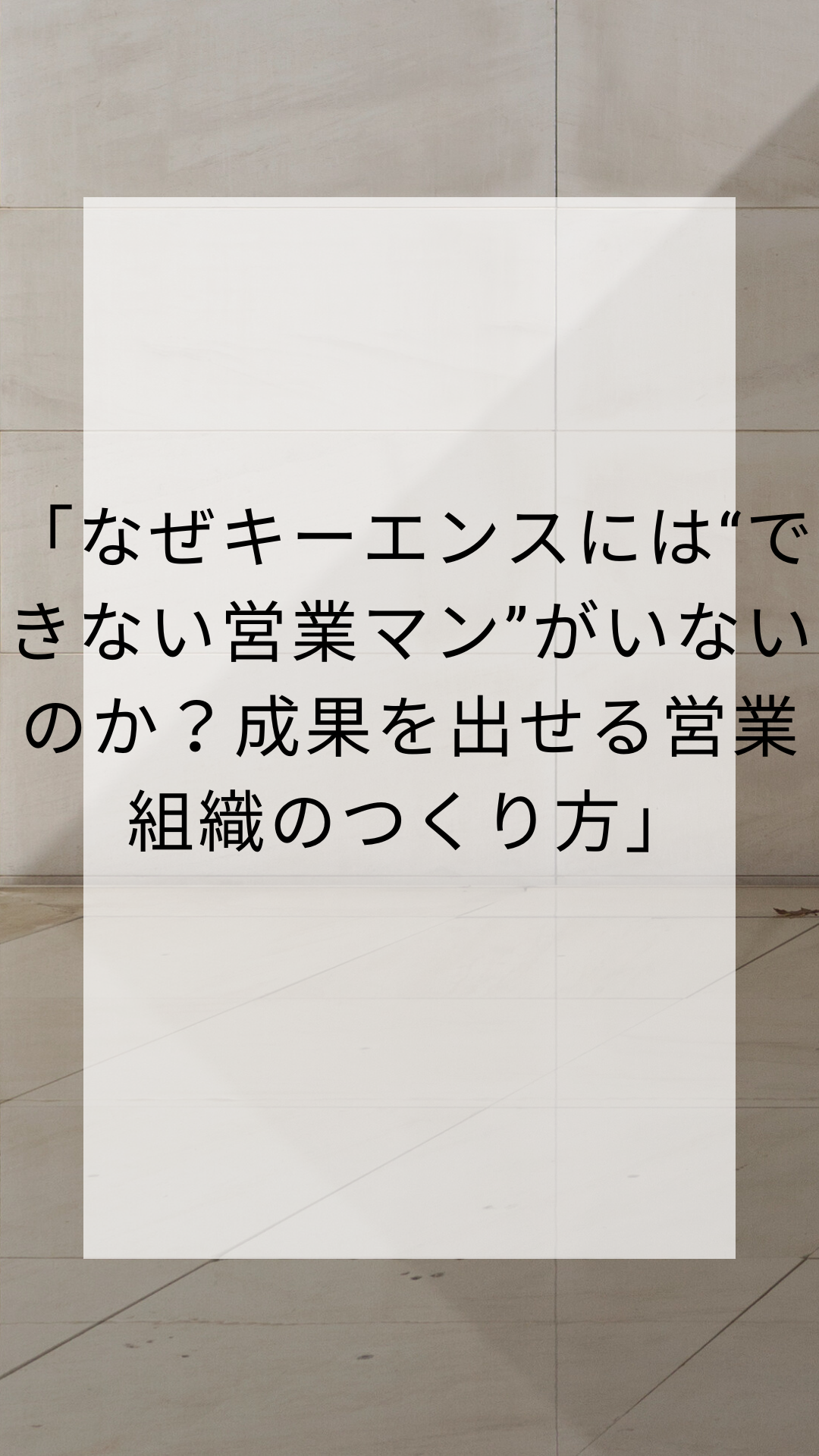
コメント